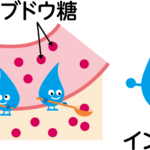過酷な猛暑に夏バテは要注意!原因から対処法まで解説
2024年7月14日

「夏は暑いもの」
四季の上ではあたりまえのことですが、近年はただ暑いという言葉だけでは言い表すことができない”猛暑”が続いています。
以前なら”猛暑”の年は”厳冬”という認識でしたが、近年は”暖冬”であることが多くて、年間を通して平均気温が上がっていることを感じます。
耐え難い”猛暑の夏”が続くだろうと考えると、”夏バテ”対策は早めにしておかないと、バテてからではとても大変です。
”夏バテ”の症状から原因、対処法まで解説します。
1. 夏バテとは?
”夏バテ”とは、真夏の気温や高い湿度によって、カラダにさまざまな不調があらわれる症状のことをいいます。
医学的に”夏バテ”という病気があるわけではなく、夏の暑さによって起こる体調不良の総称です。

その原因はさまざまですが、夏バテの症状自体が他の症状の原因になることもあり、対策してもなかなか抜け出せずに長期化することも多くあります。
また、気付かないうちに夏バテになっていることもありますので、カラダの不調を感じたら注意が必要です。
夏の暑さで体力を消耗して食欲が落ち、バテてしまうのが一般的な”夏バテ”でしたが、いまどきの夏バテは原因が多様化しており、対策しているつもりがさらなる不調を招く結果になることもあるようです。
それでは、まずは”夏バテ”の主な症状についてみていきましょう!
2. 夏バテの主な症状
”夏バテ”とひとことで言ってもその症状は多種多様です。
カラダにあらわれる不調もあれば、心の不調もありますが、”夏バテ”の主な症状をご紹介いたします。
2-1:全身のだるさと疲労感、日中の眠気
”夏バテ”の代表的な症状としてまずあげられるのは、どうしようもないカラダのだるさや、蓄積して抜けない疲労感でしょう。
動けはするのですが、常にだるさを感じていて、やる気もでない状態が続きます。
夜、睡眠をとってカラダを休めたつもりでも、疲労感が抜けきれず、朝起きたときから気分はずーんと沈んだままでグッタリ。
カラダも気分ものらないままに一日の活動をおこなうので、さらに疲労は蓄積していきます。
2-2:食欲がわかない

多くの方が経験したことがあるのではないでしょうか?
冷たいものや水分は摂れるのに、食欲がわかず朝昼晩のご飯を抜いてしまったり、残してしまったり。ちゃんと食べなきゃと思っていても、なかなか箸が進まない。
食欲がないまま少食で過ごしていると、さらに体力が落ちて倦怠感を助長してしまう結果になって食欲は落ちるばかりです。
2-3:胃腸の不調(消化不良・下痢・便秘)
夏は汗をかきやすく、体が水分を求めます。また暑い夏は体を冷やすためにアイスなどの冷たい食べ物や飲み物などが欲しくなるもの。
でも冷たいものばかリを食べていると胃腸が冷えて働きが低下し、腸での水分の吸収が悪くなり下痢の症状がでることがあります。
さらに汗をかきすぎて体内の水分が不足しても下痢になることがあり、夏の胃腸はトラブルだらけです。
また、夏に食べたくなる冷やし中華やそうめんなど、食物繊維が少ない偏った食生活を続けていると便秘になることもあります。
3. 原因
夏バテの症状はさまざまありますが、その原因は症状以上にさまざまです。
どのような原因でどのような症状があらわれるのかみていきましょう。
3-1:室内外の温度差による自律神経の乱れ
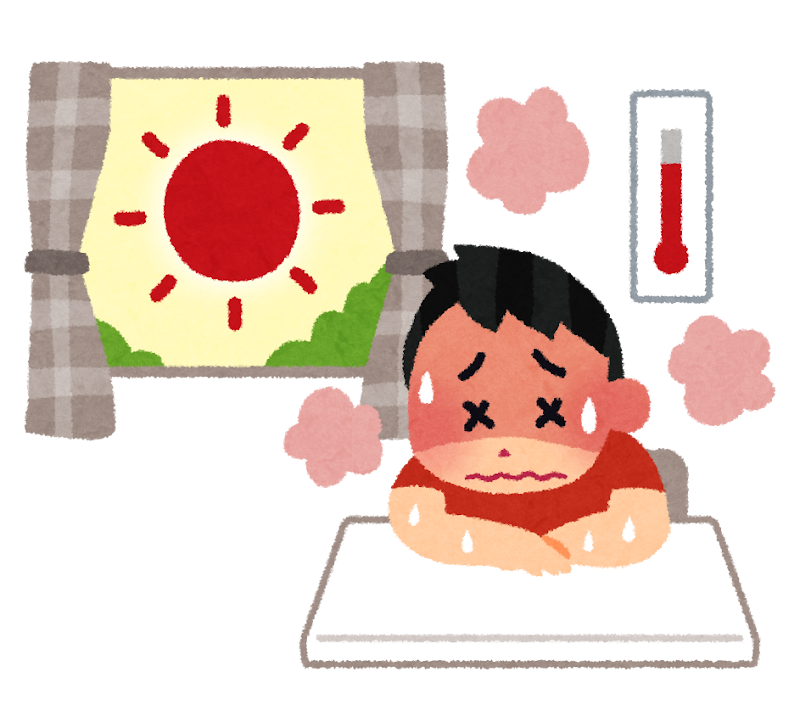
室内はクーラーで涼しく、外は猛暑で40度近い気温。室内にいても熱中症になってしまうリスクがあるほどの猛暑なので、室内でも冷房は使うべきなのですが、室内外の気温差が大きいと自律神経が乱れます。
自律神経は、普段意識しなくても動いている呼吸や体温、血圧、心拍、消化などの体の機能を調節する役割をもっています。
アクティブに活動するときには「交感神経」が働き、リラックスし休息するときには「副交感神経」が働いてバランスを保っているのです。
この機能が乱れると、睡眠や休息を取ろうとしているのに「交感神経」が働いて休まらなかったり、仕事や家事などをしないといけないのに「副交感神経」が働いて体がついてこなかったりとちぐはぐな状態になってしまいます。
動きたいのに動けない、休みたいのに休めないという状態は、とてもストレスで心にも体にも負担がかかりますよね。
夜寝ようとしているときに体が活動状態だと寝ることができず、睡眠不足になることもありますし、食後の消化・吸収には休息状態であることが必要なのですが、自律神経が乱れて活動状態だと胃腸の働きが妨げられて消化不良になることもあります。
自律神経の乱れは体の働きがちぐはぐになってしまい、だるさや疲労感、睡眠不足、胃腸の不調などさまざまな症状の原因になってしまいます。
3-2:高温多湿の環境による発汗の異常
日本の夏は湿度が高く、もっと気温が高くなる国の方からも日本の夏の暑さは耐え難いと言われるほどです。
通常、気温が高いと人は汗をかき、蒸発するときの気化熱で体温の調節をしています。
しかし、高温多湿の環境では汗の蒸発が滞ってしまい、体温調節がうまくできなくなってカラダに熱がこもってしまいます。
そのため、カラダの熱っぽさや倦怠感、頭痛などの原因になると考えられています。
また、発汗でカラダに必要なミネラル(ナトリウム・カリウム・カルシウムなど)が排出されてしまうため、疲れやすくなったり、免疫力の低下、情緒不安定、頭痛を引き起こす原因になる場合があります。
3-3:熱帯夜による睡眠不足
夜、寝る時になっても暑さが引かない「熱帯夜」。暑さで寝苦しいと感じられた経験がある方は多いのではないでしょうか。暑さのせいで寝つきが悪く、夜中に目が覚めてしまうことも。
睡眠不足で前日の疲れがとれず倦怠感の原因になるだけでなく、体内時計が乱れてしまい自律神経の乱れにもつながってしまいます。
また、熱帯夜には寝汗を多くかいて脱水状態になってしまうこともあり、熱中症になってしまう可能性もあるのでご注意ください。
3-4:冷たい食べ物・飲み物の摂り過ぎ
暑い夏には冷たい食べ物や飲み物で涼をとりたくなりますよね。
そうめんや冷やし中華は定番ですし、アイスクリームや冷たいドリンクで体の中から涼しさを感じたくなるもの。
でも冷たい食べ物や飲み物ばかりを好まれる方は要注意。胃腸が冷えてしまい働きが低下、食欲不振や消化不良をおこしたり、腸の吸収にも影響がでてしまいます。
体に必要なタンパク質やビタミンなどの栄養素が不足すると体力が落ちてしまい、倦怠感や疲労感の原因になってしまうことがあります。
水分不足にならないようこまめな水分補給は必要ですが、あまり胃腸を冷やさないようにすることが大切です。
特に冷房が効いている室内で、さらに胃腸を冷やすものを食べると胃腸の機能低下を引き起こします。胃もたれや消化不良、下痢などになりやすいのでご注意ください。
4. 対処法
夏バテにはさまざまな原因があることは知っていただけたかと思います。
暑すぎてバテ、冷やし過ぎでもバテ、短時間内での激しい環境変化に人のカラダは順応できず、自律神経が混乱して正常な反応ができなくなってしまうのが”夏バテ”といえます。
猛暑が続く夏に熱中症を避けようとおこなった対策が夏バテの原因になってしまうこともあるのは皮肉な話しですが、健やかな毎日を送るために対処法は知っておいていただきたい!
それでは夏バテにならないための対処法を具体的にみていきましょう。
4-1:エアコンの温度調節
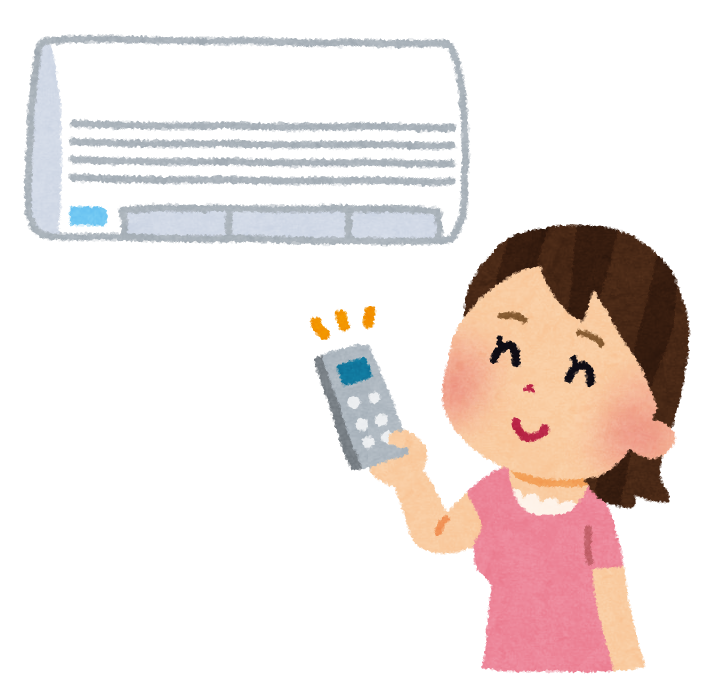
猛暑の夏は室内でも熱中症になる危険がありますので、直射日光が当たらない室内でもエアコン等で温度調節をする必要があります。
しかし、室内外の気温差が大きいと自律神経の乱れを引き起こすことがありますので、エアコンの設定温度を少し高めの設定にしましょう。
環境省では、快適性と省エネルギーの観点から、夏の室温を28℃にすることを推奨しています。
とは言え、オフィス内の空調など調整できないこともあると思います。温度設定が低すぎたり、寒さを感じる場合は一枚多めに上着を着たり、薄手のストールを羽織って冷えすぎないように体温調節をするようにしてください。
4-2:規則正しい生活と適度な運動
毎日の疲れを残さないことが夏バテ対策には有効ですが、そのためにも規則正しい生活を心がけましょう。
自律神経のバランスを整えるために、ぬるめのお風呂につかってリラックスしたり、比較的涼しい時間帯にストレッチやウォーキングなどの無理のない運動をするのもオススメです。
生活の中でオン・オフのメリハリを作ることで、生活のリズムが保たれるようになります。
暑さを我慢して激しい運動をすることは避けて下さい。汗をかきすぎて脱水症状を引き起こしたり、熱がカラダにこもりすぎて熱中症になってしまう危険性があります。
4-3:質の良い睡眠
毎日の疲れを翌日に持ち越さないためには、質の良い睡眠がとても大事になります。
規則正しい生活でもオススメしましたが、ぬるめのお風呂につかってリラックスしましょう。湯船につかると血行が良くなって体温が上がり、副交感神経が優位になりますので、心身ともにリラックスでき、眠りやすい状態になります。
また、暑さのために寝苦しいときは、エアコンで室温を調節するのがオススメです。ただ、寝る前に室温を調節しておくか、睡眠時にタイマーで稼働時間を決めておくなどして、体を冷やし過ぎないようにしましょう。
寝入りがよく、朝までぐっすりと眠れるのがベストです。
4-4:栄養バランスのよい食事
夏に好まれる冷たい食べ物と言えば、そうめんや冷やし中華などの麺類が多いと思います。のど越しもさわやかで、涼を感じれるのもグッドです。
でも炭水化物に偏った食生活では、必要な栄養素が不足してしまいます。たんぱく質やビタミン、特にミネラルは発汗によってただでさえ不足しがちです。
必須の栄養素が不足すると疲れが回復できずに溜まってしまいます。疲れが溜まっていると食欲不振になってしまうので悪循環におちいりがちです。
特に積極的に摂取していただきたいのはビタミンB1です。
ビタミンB1は、糖質をエネルギーに分解するのを助ける働きがあり、疲労回復に役立ちます。豚肉や大豆製品などに多く含まれているので、積極的に摂取しましょう。
そして、ビタミンB1と一緒に摂取していただきたいのがアリシンです。玉ねぎやニンニクなどに多く含まれていて、ビタミンB1の体内吸収を助けてくれます。
みやびのすっぽんサプリ『はればれ』にも「ビタミンB1」と「アリシン」が含まれています。食欲がわかない方や上記食材を好まれない方はサプリメントで摂取していただくことをオススメしています。
4-5:こまめな水分補給
夏は汗をかきやすく、水分不足になりがちです。水分は人のカラダの約60%を占めているとても大切なもの。水分が不足して脱水症状になると、のどの渇きだけではなく、めまいや立ちくらみに始まり、ひどくなると意識障害を起こすこともあります。
暑さで汗をかいてしまう夏は水分補給をしっかりとしていただきたいものですが、一度に多量の水を飲むことはオススメできません。
多量の水分を一気に飲んでもあまり効果はなく、むしろ体内のミネラルバランスが崩れてしまって体調不良を引き起こすこともあるので注意して下さい。
水分補給はこまめにおこなうのが大切です。
20~30分に一回水分補給を行うことが推奨されています。
汗を多量にかく方は、ミネラル不足にもなりますので、一緒に塩分を補給することをオススメします。
4-6:胃腸の負担を減らす
夏バテの中でも「胃腸バテ」と別に呼ばれるくらい気をつけたいのが胃や腸などの消化器官の疲労です。
夏バテ対策には栄養バランスのよい食事とこまめな水分補給が大切なのですが、胃腸が疲れて機能低下をおこしていると、消化不良で胃の負担がさらに増えるうえに、水分や必要な栄養素の吸収にも影響がでてきます。
夏に下痢などの便通異常になるのはこのためなのです。
「猛暑の中で体力を奪われているときにこそ、しっかりと食べなくては!」と、がんばって食べていることが負担になり、むしろ逆効果になったりも。
胃腸の負担になるものとしては下記のようなことがあります。
・冷房が効きすぎた室内で体全体を冷やしすぎる
・冷たいものばかリを摂取して胃腸を冷やしすぎる
・胃腸が弱っている時に消化に悪いものを食べる
猛暑の中では室内でも熱中症になることがあるので、冷房で温度調節することが必要なのは前に書きましたが、体を冷やしすぎると胃腸トラブルの原因にもなるので注意が必要です。
冷房で体が冷えているところに冷たいものを摂取すると、さらに胃腸が冷えてしまい負担が増えてしまいます。
胃腸バテにならないための対策としては、体、特に胃腸を冷やし過ぎないことが大切です。
冷房設定を調整して、室内温度は28℃くらいで冷えすぎない設定にしましょう。
夏の定番ともいえるそうめんや冷やし中華などの冷たい麺類、アイスクリームや冷たいドリンクは涼しくなってよいのですが、胃腸が冷えすぎないようにお味噌汁や温かいお茶など、食事の中に温かい食べ物や飲み物も一緒に摂るようにしましょう。
一度胃腸に問題が発生すると、回復に必要な栄養素の吸収にも影響が出てしまうために栄養素不足になり、消化不良なのに消化に必要な酵素の生成にも影響がでてしまってさらに消化不良になってしまう負の連鎖に陥ってしまいます。
特に40歳を超えた中高年世代は要注意。体内で作られる酵素の量は加齢とともに減少していくので、胃腸バテになってしまうとなかなか抜け出せないなんてことも。
まずは胃腸のケアから始めることが大切になりますが、普通の食事では難しいのでサプリメントで補給するのがオススメです。
体を支える発酵酵素と、体内の環境を整える乳酸菌を配合した『みやびの贅沢な植物酵素100』であれば、胃腸バテの心強い味方になってくれます!
お客様の健康を願い、約5年の歳月をかけて作ったみやび自慢のサプリメント。夏バテだけではなく、日々の活力になるペーストタイプのおいしい酵素です。
せっかくなので、ご愛用いただいているお客様から届いたお声を一部ご紹介したいと思います。
お1人目は福島県のK.Sさん、女性の方です。
今年も猛暑が続き辛い夏でした。(福島は暑いのです)毎年夏の終わりに体調をくずしていたので植物酵素100を飲んでいて、疲れがやわらいだように思います。先日娘と上京した時、帰りは疲れ果ててしまうのですが、それがなかったように思います。これからも続けていきます。よろしく。
続いて、70歳になられたM.Mさん。こちらも女性の方ですね。
すこぶる元気です。古希になりましたが同級生とか、周りの人に何でそんなに元気なの?と言われます。酵素を飲み続けているからだと思います。これからも継続していきたいです。ありがたいです。
76歳で自治会長をされている元気なH.Kさん。
今年、喜寿、金婚の年で480戸の自治会長をして頑張っています。先日、後期高齢者の運転免許更新で認知機能検査を受けました。結構難しかったのですが、結果は97点。これもいつも飲んでる植物発酵100のおかげでしょう(笑)
最後に、80歳になられてもダンスを楽しまれているT.Iさんです。
80才になります。7年ぶりにダンスパーティーに出掛けました。見学と音楽だけでも楽しもうと思いましたが、先生のリードでスタンダードラテン何回も踊れました。自分でもビックリしました、健康は有難いです。
ご愛用のお客様からもこのようなお声をいただいていますので、夏バテ・胃腸バテだけではなく、健やかな毎日のお役に立てると信じています。
腸には脳の次に神経細胞が多くあり「第二の脳」と呼ばれるほど敏感な臓器です。脳との関係も密接で、脳が受けたストレスは腸に、腸の不調は脳にも影響を及ぼしてしまいます。
夏の暑さに気持ちで負けないためにも、胃腸の負担を減らして元気に過ごしたいですね。
5. まとめ
決してなりたくてなるわけではない「夏バテ」ですが、一度なってしまうと夏バテの症状自体が別の症状を引き起こしたりと複雑に絡み合っているので、対策しているようでも実は見当違いであることも多いようです。
何が原因で症状が出ているのかを考えてみても、イマイチはっきりしないときもありますが、人間、食がカラダを作っています。
まずは普通に食事ができることを目標として対策するのが良いのではないかと考えています。
今回ご提案させていただいた対処法の中には、お仕事の関係でむずかしい方もいらっしゃると思います。
それでも、出来る限りの対策をして、猛暑の夏を健やかに過ごしていただきたいと考えています。
https://brand.taisho.co.jp/contents/tsukare/70/
https://aih-net.com/pikarada/lifestyle/199/
https://alinamin-kenko.jp/navi/navi_kizi_natsubate.html
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/kateico2tokei/energy/detail/06/
https://www.city.mito.lg.jp/page/56263.html
https://www.shinyuri-hospital.com/column/eiyou/magazine_201808.html
https://www.eisai.jp/articles/stomach_mechanism/advice10
https://kenko.sawai.co.jp/healthcare/201907.html