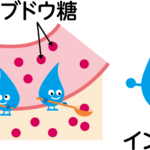便秘対策、間違っていませんか?解放されたい方必見!
2024年2月14日

みやびにご連絡をいただくお客様の中には、便通でお悩みの方が多くいらっしゃいます。
一週間以上出ないとおっしゃられる方も多く、不快感だけではなく、膨満感や腹痛などで苦しまれているのは、とても心配になります。
お客様の状況に合わせて話をさせていただくことが多いのですが、便通・便秘対策の大きな柱は下記の2点に集約できます。
1. 便を柔らかくする
2. 腸の蠕動運動を活発にする
そこで今回は、上の2点を軸に、便秘の基本的な対策をお伝えしたいと思います。
1. 便を柔らかくする
便が硬いと腸の壁との摩擦を起こしやすく、また腸の蠕動運動を阻害して停滞しやすくなります。
便にある程度の柔らかさを持たせることが大切なのですが、そのためには「水分」と「食物繊維」の摂取が必要になります。
水分

便の約70~80%は水分でできています。十分な水分を摂ることで、便が硬くなるのを防ぎ、スムーズな排出を促します。
便が硬くなると、腸壁を傷つけたり、排便時に痛みを感じやすくなったりする可能性があります。
1日の水分摂取量目安
個人差はありますが、1日に1.5~2リットルの水分を摂ることを目安にしましょう。
水だけでなく、お茶、スープ、果汁なども水分補給に役立ちます。
注意すべき飲み物
・砂糖がたくさん入ったジュース
糖分は悪玉菌のエサとなり、悪玉菌が増殖しやすくなります。悪玉菌は有害物質を産生し、腸の働きを阻害するため、便秘の原因となります。
・カフェインを含むジュース
コーヒーや紅茶など、カフェインを含む飲み物は、利尿作用があり、体内の水分を排出してしまうため、飲みすぎには注意が必要です。
食物繊維
特に水溶性食物繊維は、腸内で水分を吸収してゲル状になり、便を柔らかくする効果があります。
水溶性食物繊維は、海藻やリンゴ・バナナ・オレンジなどの果物、豆類などに多く含まれています。
2. 腸の蠕動運動を活発にする
腸内を便が移動するには、腸の蠕動運動(収縮して内容物を押し出す動き)が活発におこなわれる必要があります。
腸が元気で健康であるには、善玉菌を育て腸内環境を改善する他、生活習慣にも気を遣って活発にしましょう。
水分
水分は腸の潤滑油です。十分な水分があることで、便は腸壁をスムーズに滑りやすくなり、腸の蠕動運動(ぜん動運動)が活発になります。
食物繊維

不溶性食物繊維は、腸内で水分を吸収して便の量を増やし、腸壁を刺激して蠕動運動を促します。
また、水溶性食物繊維は腸内の善玉菌のエサとなり、腸内環境を良好に保ちます。腸内環境が整うことで、腸の働きが活発になります。
不溶性食物繊維は、玄米や全粒粉、ごぼう・ほうれん草などの野菜、野菜の皮などにに多く含まれています。
乳酸菌・ビフィズス菌(善玉菌)
腸内環境の改善
乳酸菌は、腸内環境を酸性化し、善玉菌を増やすことで、腸内フローラを整えます。健康な腸内フローラは、腸の蠕動運動を円滑にする上で重要な役割を果たします。
短鎖脂肪酸の生成
乳酸菌は、食物繊維を分解して短鎖脂肪酸を作り出します。
短鎖脂肪酸は、腸の細胞に栄養を与え、腸の機能を活性化させる働きがあります。これにより、間接的に腸の蠕動運動が活発になる可能性があります。
代表的な短鎖脂肪酸には、酢酸、プロピオン酸、酪酸などがあり、様々な働きがあります。
腸壁の強化
乳酸菌は、腸壁を強化する働きもあります。健康な腸壁は、蠕動運動をスムーズに行う上で重要です。
生活習慣
運動
 軽い運動は、自律神経のバランスを整え、血行が良くなって腸への血流も増加します。また、セロトニンなどの神経伝達物質が分泌されるので、腸の働きを活発にする効果があります。
軽い運動は、自律神経のバランスを整え、血行が良くなって腸への血流も増加します。また、セロトニンなどの神経伝達物質が分泌されるので、腸の働きを活発にする効果があります。
規則正しい食事
食事を規則正しく摂ることで、腸内細菌は食事に合わせたリズムで活動し、腸内環境を安定させます。
十分な睡眠
睡眠不足は自律神経のバランスを崩し、腸の働きを抑制する可能性がありますので、十分な睡眠を心がけましょう。
3. 水分と食物繊維と乳酸菌の相関図
| 便の柔らかさ | ||||
| ▲ 柔らかさUP (吸収) ▲ |
▲ 柔らかさUP (ゲル状) ▲ |
|||
| 水分 | ▶吸収▶ | 水溶性 食物繊維 |
▶エサ▶ | 善玉菌 (乳酸菌・ビフィズス菌) |
|---|---|---|---|---|
| ▶吸収▶ | 不溶性 食物繊維 |
|||
| ▼ 潤滑油 ▼ |
▼ 便増量 刺激 ▼ |
▼ 短鎖脂肪酸 腸内フローラ ▼ |
||
| 腸の蠕動運動 | ||||
| ▲ サポート ▲ |
||||
| 生活習慣 (運動・規則正しい食事・睡眠) | ||||
水分と食物繊維、善玉菌の相関関係は上の図のようになっています。
この相関関係によって促される腸の働きを、運動や睡眠などの生活習慣で補助して、便秘状態を改善するイメージになります。
「みやびの植物酵素100」に含まれる「難消化性デキストリン」は水溶性食物繊維に分類されます。
4. 世代別の便秘の原因の傾向と対策
便秘の原因は、年齢によって異なります。これは、食生活、運動習慣、身体機能の変化などが、年齢と共に変化するためです。
それぞれの世代における便秘の原因とその対策について、詳しく見ていきましょう。
4-1:乳幼児期
乳幼児期に起こりやすい便秘の原因
・離乳食への移行
母乳やミルクから固形食へ変わることで、消化に時間がかかり、便秘になることがあります。
・便意を我慢する
トイレトレーニングの時期と重なり、便意を我慢してしまうことがあります。
・運動不足
長時間お座りや寝たきりの状態が続くと、腸の動きが鈍くなります。
乳幼児期に便秘になった時の対策
・食事
食物繊維を多く含む離乳食を心がける、水分を十分に与える。
・生活習慣
規則正しい排便習慣を身につける、適度な運動を促す。
4-2:学童期
学童期に起こりやすい便秘の原因
・食生活の偏り
好き嫌いが多い、間食が多いなど、バランスの悪い食事は便秘を引き起こす可能性があります。
・運動不足
長時間ゲームやスマホをしているなど、運動不足が便秘の原因となることがあります。
・ストレス
学校での人間関係や勉強のストレスが、便秘の一因となることがあります。
学童期に便秘になった時の対策
・食事
バランスの取れた食事を心がける、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂る。
・生活習慣
規則正しい生活リズムを送り、十分な睡眠をとる、適度な運動をする。
・ストレス
リラックスできる時間を設ける、悩みを相談できる相手を見つける。
4-3:青年期
青年期は、成長期であり、生活習慣が大きく変化する時期です。そのため、便秘に悩む人も少なくありません。
青年期に起こりやすい便秘の原因
・食生活の乱れ
不規則な食事、外食の増加、偏食など、バランスの取れた食事ができていないことが原因の一つです。特に、食物繊維が不足すると、腸の動きが鈍くなり、便秘になりやすくなります。
・運動不足
長時間座って勉強や仕事をする、運動不足が原因で腸の蠕動運動が弱まり、便秘になることがあります。
・ストレス
入試、人間関係、将来への不安など、様々なストレスが便秘を引き起こすことがあります。ストレスは、自律神経のバランスを乱し、腸の働きを低下させます。
・睡眠不足
睡眠不足は、自律神経のバランスを乱し、腸の働きを抑制します。
・水分不足
水分が不足すると、便が硬くなり、排便が困難になります。
・便意を我慢する
忙しい時や場所によっては、便意を我慢してしまうことがあります。
青年期に便秘になった時の対策
・バランスの取れた食事
食物繊維を多く含む野菜、果物、全粒穀物を積極的に摂りましょう。
・水分補給
1日1.5リットル~2リットルの水をこまめに飲みましょう。
・規則正しい生活
毎日決まった時間に寝起きし、十分な睡眠をとりましょう。
・適度な運動
ウォーキングや軽い運動を習慣化しましょう。
・ストレス解消
ヨガや瞑想など、リラックスできる方法を取り入れましょう。
・便意を感じたら我慢しない
便意を感じたら、すぐにトイレに行きましょう。
4-4:中高年期
中高年期に起こりやすい便秘の原因
・運動不足
加齢とともに運動量が減り、腸の動きが鈍くなる。
・食生活の変化
噛む力が弱くなり、食物繊維が不足しがちになる。
・薬の副作用
高血圧や糖尿病の薬など、便秘を引き起こす可能性のある薬を服用している場合がある。
・ストレス
仕事や人間関係のストレスが、自律神経のバランスを崩し、便秘を引き起こす。
中高年期に便秘になった時の対策
・食事
食物繊維を多く含む食品を積極的に摂る、水分を十分に摂取する。
・運動
ウォーキングや軽い運動を習慣化する。
・生活習慣
規則正しい生活リズムを心がける、リラックスできる時間を設ける。
・薬の飲み合わせ
医師や薬剤師に相談し、便秘の副作用が出る可能性のある薬について確認する。
4-5:高齢期
高齢期にに起こりやすい便秘の原因
・加齢による体の変化
腸の蠕動運動が低下する、水分吸収量が増えるなど、加齢に伴う体の変化が便秘の原因となる。
・病気
糖尿病、大腸がんなど、様々な病気が便秘の原因となることがある。
・薬の副作用
高血圧、心臓病の薬など、便秘を引き起こす可能性のある薬を服用している場合がある。
高齢期に便秘になった時の対策
・食事
食物繊維を多く含む食品を積極的に摂る、水分をこまめに摂取する。
・運動
体力に合わせた運動を続ける。
・生活習慣
規則正しい生活を送る、排便の時間を決めてトイレに座る。
・医療機関への相談
便秘が続く場合は、医師に相談する。
5. まとめ

便秘対策を2つの柱を中心に書きましたが、毎日の水分摂取量と食事のバランスと量が大きく関わっています。
特に中高年期以降は食が細くなり、便の量が減少して腸の蠕動運動が刺激されにくくなる傾向にあります。食物繊維が不足しがちなので、積極的に摂取するように心がけましょう。
しかし、食事の量を増やすのは大変です。無理に食べて胃腸に負担をかけて体調を崩してしまうこともありますので、食物繊維や乳酸菌、酵素などのサプリメントを上手に利用して、便通改善を目指しましょう。